「時間がないから無理」は思い込みだった。
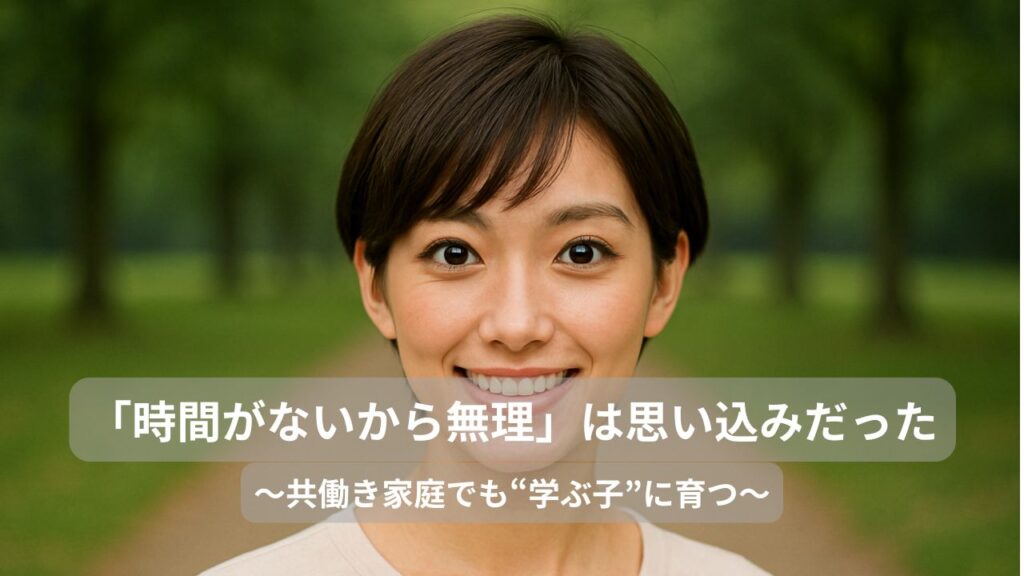
共働き家庭でも“学ぶ子”に育つ、科学的に正しい関わり方
「子育てにもっと時間をかけたい」けど…
「子どもにしっかり向き合いたい。でも、仕事もあるし、家事もある。気づけば一日が終わってしまう…。」
そんな悩みを抱える共働きの親は、あなただけではありません。私たちは“理想の子育て”と“現実の時間不足”の間で、いつも葛藤しています。
中には「専業主婦の家庭の方が子どもの教育に有利」「高学歴の親の子は、やっぱり勉強ができる」と感じる方もいるかもしれません。でも、それって本当なのでしょうか?
実は、最新の研究では「親の働き方や学歴」よりも「家庭での関わり方」が、子どもの学力や自律性に強く影響することが明らかになっています。
親の学歴・働き方は「決定要因」ではない
たとえば、東京大学のCedep(子どもの発達に関する研究センター)が2021年に発表した調査では、親の学歴や働き方そのものが、子どもの学力や思考力に大きく影響するという証拠はないことが示されています。
同じく、国立教育政策研究所(2019年)の調査でも、「父親の学歴や職業と子どもの学力との相関は極めて低い」と報告されています。
つまり、“家庭にどれだけ親がいるか”や“学歴の高さ”ではなく、
日常の中で、親がどれだけ「肯定的に関わっているか」が鍵になるのです。
「1日10分」が子どもを変える
忙しい共働き家庭でも大丈夫。実は、1日10分の“質の高い関わり”があれば、子どもの「やる気」や「思考力」は大きく伸びるのです。
具体的には、こんな時間を持つことが効果的です:
- 夕食後に「今日どんなことがあった?」と聞く
- 寝る前に1問だけクイズを出す
- 子どもが話したことに「へえ!なんでそう思ったの?」とリアクションする
これらはほんの5〜10分でできますが、脳内のドーパミン報酬系を刺激し、「学ぶって楽しい!」という記憶をつくる手助けになります。
(※出典:Benware & Deci, 1984/前頭前野の活性と報酬系に関する脳科学研究)
自律的に学ぶ子どもを育てる“関わり方のコツ”
① 子どもに「選ばせる」
教育心理学の理論「自己決定理論(SDT)」では、人は「自分で選んだこと」にこそやる気を感じるとされています。
たとえば:
- 「どっちのドリルからやる?」と選ばせる
- 「今日は算数と国語、どっちがいい?」と聞く
- 「終わったら何する?」とごほうびを一緒に決める
このように、学習の“設計者”を子どもに任せることで、自律性が育ちます。
② 「努力」や「工夫」をほめる
カリフォルニア大学の心理学者キャロル・ドゥエックによる「成長マインドセット」の理論では、「結果」ではなく「プロセス」に注目することが、学習意欲の持続に効果的だとされています。
たとえば:
- 「コツコツ頑張ってたね」
- 「間違えても最後までやってたの、えらい」
- 「自分で工夫してたね!」
こうした声かけは、子どもに「自分は成長できる」という感覚を与えます。
「遊び×学び」が最強のツール
さらに効果的なのは、「遊び」と「学び」を融合させることです。
- 恐竜好きなら図鑑や動画を一緒に調べる
- キッチンで料理をしながら重さや温度を学ぶ
- お出かけ先で地図や看板を読み取る
こうした「楽しい体験」は、記憶に残りやすく、モノのごほうびよりも学びの内発的動機づけが高まることがDeciらの研究でも示されています。
あなたの10分が、子どもの未来になる
共働きだから時間がない――それは事実かもしれません。
でも、それが「不利になる」というのは、ただの思い込みです。
子どもに必要なのは、“長い時間”ではなく、“心の通った短い時間”。
1日10分でも、親からの「興味」「応援」「信頼」があれば、子どもは自ら学び、自ら成長していく力を育てていきます。
今のあなたにできることから、始めてみませんか?
その10分が、子どもの一生の“学びの土台”になるのです。
🔖参考文献一覧(簡略版)
- 東京大学Cedep「子どもの発達と家庭環境に関する研究」(2021)
- 国立教育政策研究所「全国学力・学習状況調査報告書」(2019)
- Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior
- Dweck, C. (2006). Mindset: The New Psychology of Success
- Benware, C.A. & Deci, E.L. (1984). Quality of Learning With an Active Versus Passive Motivational Set



