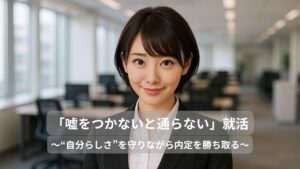「私ばかり頑張ってる」から抜け出す育児術

専業・育休ママの“しんどさ”を軽くする共感と実践のヒント
はじめに|「私は家にいるのに、なぜこんなに疲れてるんだろう」
専業主婦、もしくは育休中。
経済的にはギリギリながらも夫の収入でなんとかやりくりできている。
だけど、毎日どこか息が詰まるような思いをしている。
――それはきっと、「育児=ひとりで背負うもの」になっているから。
「家にいるんだから」「休めていいね」と言われるけど、実際には1日中気が抜けない。
夜泣きの対応、離乳食、洗濯、掃除、子どもの相手…。
休む時間なんて、どこにもない。
このエッセイでは、そんな「しんどさ」に寄り添い、今すぐできる具体策を紹介していきます。
第1章|“孤独な育児”が心を削るワケ
厚労省の調査では、**7割以上の母親が「育児の孤独を感じている」**というデータがあります。
特に専業主婦や育休ママは、社会との接点が減ることで「自分だけが取り残されてる」と感じやすい。
加えて、経済的に余裕がないと、気軽に外出や一時保育に頼ることもできず、精神的・物理的な孤立が進みやすいのです。
▶解決のヒント:
- 地域の「子育てひろば」「子育て支援センター」など、無料の場を積極的に活用
- SNSでもいい。育児アカウントで気軽に気持ちを吐き出すだけで、心が軽くなることも
第2章|夫婦間の“温度差”がすれ違いを生む
夫は外で働いている、私は家で子どもを見ている――
この構図は、一見分業に見えますが、**見えない“労働格差”**を生みやすい。
夫:「こっちも仕事で疲れてる」
妻:「こっちこそ24時間休みなしだよ」
このままでは、対立が深まるだけ。
ポイントは、“感情”をぶつけるのではなく、“事実”を伝えること。
▶解決のヒント:
- 「今日どんなことをやったか」を簡単にメモしてLINEで共有
- やっていることの“見える化”で、理解と感謝が生まれる
第3章|経済的にも時間的にもキツい中での「分担」の現実解
「分担」と言うと、しっかり半分こしなきゃ!と思いがちですが、完璧を目指すと続きません。
そこでおすすめなのが、“曜日制”や“時間帯制”の分担方法。
例えば、
- 平日朝の子どもの準備はパパ
- 休日は午前中だけでも夫が担当
- 家事リストを“タスクボード”にして貼る
責任範囲を明確にすることで、「気づいた方がやる」文化からの脱却ができます。
第4章|“パパが関わらない”影響と、できることから始める方法
父親の育児参加は、子どもの**非認知能力(やる気・忍耐・社会性)**にも好影響があります。
ベネッセ教育総研の調査では、父親とのふれあい頻度が高い子の方が、社会性や自己肯定感が高いという結果も。
ただ、「いきなり全部やって」と言っても難しいのが現実。
だからこそ、「ここだけはパパの担当」と明確にすることが大切。
▶取り組み例:
- 平日:寝る前の絵本担当(5分)
- 週末:1日30分の外遊び当番
第5章|お金をかけずにできる発達支援法
知育玩具や教材は高くて手が出せない…。
そんな時こそ、**“暮らしの中にある知育”**を意識してみてください。
- 洗濯バサミで色・形あてゲーム
- 空き箱でお店屋さんごっこ
- ごはんの時間に食材クイズ
- 一緒に掃除機をかけて「障害物レース」ごっこ
体を動かす遊びは、バランス感覚や筋力、空間認知力の育成にも繋がります。
第6章|ママ自身の“心のメンテナンス”が大事
育児は、自分の“感情”と向き合う連続です。
何もしてないのに涙が出る。イライラが止まらない。
それは、限界に近づいてるサインかもしれません。
▶おすすめ習慣:
- 「よかったこと日記」:たった1行でもOK
- 10分だけ外へ出て、日光を浴びる
- 月に数回でも、在宅アンケートなどで社会とつながる感覚を持つ
「私はちゃんと生きてる」――この実感が、心の安定に繋がります。
第7章|“しんどい育児”を“楽しめる瞬間”に変える方法
最後に大切にしたいのは、「楽しめる瞬間を、ちゃんと味わうこと」。
育児は大変。でも、笑ってくれる顔、手を握ってくれる小さな手、泣きながら抱きついてくるその温もり…。
その全部が、今しか味わえない宝物です。
▶工夫例:
- 成長記録を「3行日記+写真」で残す
- 家事を“ごっこ遊び”にして子どもと一緒に
- 自分への“プチごほうび”時間を習慣に
おわりに|「私ばかり頑張ってる」じゃなくていい
あなたが頑張っていることは、ちゃんと子どもに届いています。
でも、ひとりで頑張らなくていいんです。
育児は、もっと分かち合っていい。
手を抜いても、休んでも、笑ってもいい。
「完璧」より「続けられる」こと。
そして、「チームで育てる」ことを諦めないで。
心がしんどくなったら、またこのページに戻ってきてくださいね。