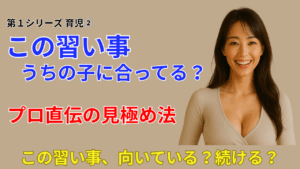「なんでこんなに高いの?」から始まる、親子の選挙の話

—— 参院選2025、物価高をどう考える?
「ママ、このお菓子、前より高くなった?」
「うん、なんか値段、また上がってる気がするね…」
こんな会話、最近の家庭ではきっと珍しくないでしょう。
そして、ふと気づけば「選挙」がすぐそこに。
でも、「どの政党が、どんな政策をしているのか」なんて、ニュースでは難しい言葉ばかりで、子どもに説明するのはなかなかハードルが高いものです。
そこで今回のエッセイでは、親子で“物価高と選挙”を考えるために、今の状況と各政党の対策をやさしく、でも正確にまとめてみました。
物価高ってどうして起きるの?
「物価高(ぶっかだか)」とは、モノの値段が全体的に上がっていくこと。
たとえば、
- パンや牛乳の値段が上がった
- 電気代やガソリン代が高くなった
- 学校の給食費もじわじわ値上がりしている
これは、日本だけの問題ではありません。
エネルギーや食べ物の多くを外国から買っている日本では、
・円安(日本のお金の価値が下がる)
・戦争や異常気象(輸入が難しくなる)
など、世界の出来事が、私たちの暮らしに影響しているのです。
各政党の「物価高対策」をくらべてみる
参議院選挙では、さまざまな政党が「物価高から守ります!」と主張しています。
でも、その中身をよく見ると、アプローチやリスクが全く違います。
以下、主要政党ごとの対策と、その“見えにくいリスク”も整理してみましょう。
🟩 自民党・公明党(与党連合)
どんな政策?
・1人2万円の給付金、さらに子育て世帯などには上乗せ
・電気・ガス・ガソリンの補助金
・企業の国内投資を支援し、生産性をアップさせる狙いも
良いところ
・すぐに現金が届く
・光熱費の負担も減ってありがたい
・企業も少し元気になれる
気をつけたい点
・税金をたくさん使うため、将来の増税や社会保障のカットにつながるかも
・企業が「補助金があるから努力しなくていい」となり、生産性が上がらないリスクも
・「また選挙前のバラマキ?」と、国民の信頼が下がることも
🟦 立憲民主党
どんな政策?
・食料品の消費税を0%に(一時的)
・低所得者向けの給付金
・最低賃金の引き上げ+中小企業支援
・お金持ちや大企業への課税を強化
良いところ
・日常の食費を下げるのは、とても分かりやすい支援
・格差是正を意識した政策構成
気をつけたい点
・消費税は国の大事な収入源。これが減ると、医療や年金、教育の予算が減るかも
・対象品目の線引きや、レジの変更で混乱が出る可能性も
・減税が終わったあとの“価格の戻り”が逆に負担になることもある
🟨 日本維新の会
どんな政策?
・食料品の消費税ゼロ(2年間)
・行政改革(公務員数や議員報酬を削る)
・規制緩和で民間の活力を高める
良いところ
・「無駄を削って、その分、国民に還元する」姿勢
・官から民へのシフトをめざす
気をつけたい点
・公務員の士気が下がったり、人材が流出する可能性
・規制緩和で中小企業が苦しむことも
・改革がうまく進まなければ、期待が失望に変わるリスクも
🔴 共産党・れいわ・国民民主・社民党など
どんな政策?
・消費税を5%に引き下げ(または廃止)
・最低賃金を1700円に
・ベーシックインカム型の給付金導入(れいわ)
・非正規雇用の待遇改善(社民)
良いところ
・生活の底上げに重きを置いている
・再分配で格差是正をはかる姿勢が強い
気をつけたい点
・消費税は国の収入の約20%。一気になくすのは現実的にかなり大変
・給付や賃上げで“お金のばらまき”が過ぎると、インフレがさらに悪化する可能性
・財源がはっきりしないと、信用不安や円安が進むことも
政策には「見える効果」と「見えないリスク」がある
大事なのは、どの政策にも「良い面」と「心配な面」があるということ。
たとえば…
| 政策の表 | 隠れた負担・リスク |
|---|---|
| 現金給付 | 財源が足りず、後で増税に? |
| 消費税ゼロ | 医療や教育の予算が削られる? |
| 賃金アップ | 中小企業の倒産や雇用減少の懸念 |
| 補助金政策 | 企業が努力しなくなる可能性 |
子どもと一緒に「考える力」を育てよう
「この政党、なんでこういう政策をするんだろう?」
「そのツケは誰が払うのかな?」
「目先の得と、未来の負担、どっちを重視したい?」
こんな問いかけをしながら、
お子さんと一緒に“選ぶ力”を育てていけるといいですね。
政治や経済は決して「大人だけの話」ではありません。
家族で話すことが、未来を考えるいちばんの学びになります。