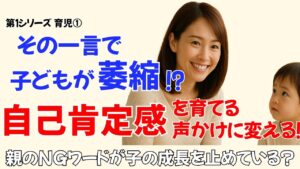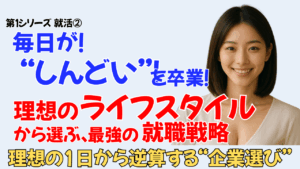習い事が“親の満足”になっていないか?
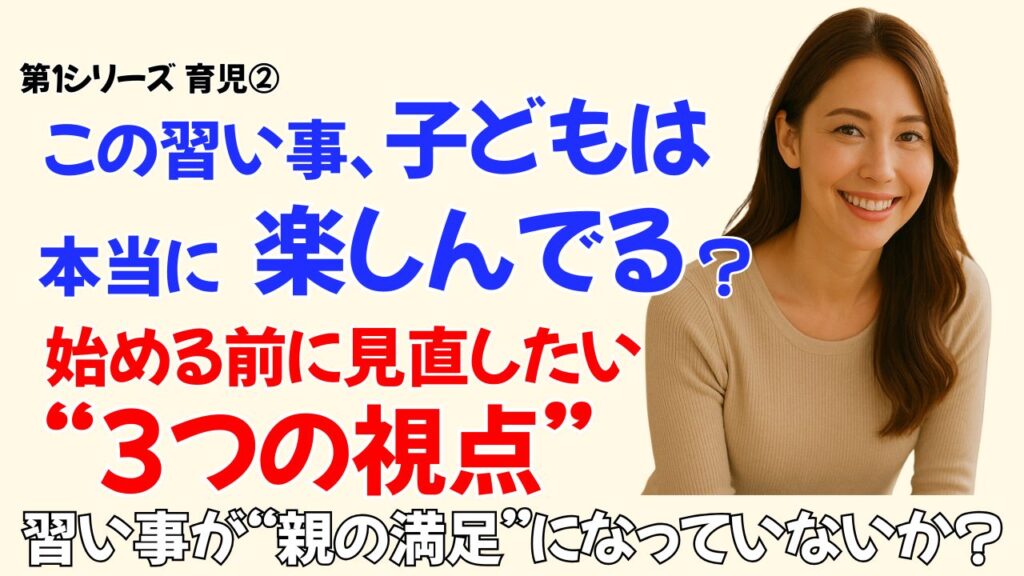
「子どもの将来のために」と始めた習い事。でもふとした時に、子どもが言う「やりたくない」の一言にドキッとしたことはありませんか?
もしかしたら、それは“親の満足”が前面に出すぎていたサインかもしれません。
今回は、習い事を見直すための5つの視点をご紹介します✨
親の夢を、子どもに託していない?
「私も子どもの頃ピアノが習いたかったから」「英語ができたら将来役立つから」——その気持ち、決して悪いことではありません。でも、それが“親の夢”や“未練”からきていないか、一度立ち止まって考えてみてください。
子ども自身が「やってみたい!」と言ったわけではない場合、どうしても長続きしない傾向があります。
親の想いと、子どもの気持ちは必ずしも一致しません。だからこそ、“誰のための習い事か”を問い直すことが大切なんです。
「やりたくない」は立派なサイン
「今日は行きたくない」「疲れた」——こんな言葉が出てきた時、「甘えてるだけ」と片付けていませんか?
実はそれ、子どもなりのSOSかもしれません。
子どもは自分の感情を言葉にするのがまだ難しいからこそ、些細な一言や態度に本音が表れます。
“行きたくない”の背景には、「楽しくない」「うまくできなくて苦しい」「自信が持てない」など、さまざまな感情が隠れているのです。
本人は、楽しめている?
子どもが笑顔で取り組んでいるか、終わったあとに「今日、楽しかった!」と言っているか。
その様子を観察するだけでも、習い事が合っているかが見えてきます。
「どんなときが嬉しい?」「何が好き?」と問いかけることも有効です。
評価や成果に目を向ける前に、まずは“本人の感じていること”に耳を傾けてみましょう。
やめるのは、逃げじゃない
「一度始めたら続けなきゃいけない」と思っていませんか?でも、合わないことを無理に続けさせるのは、学ぶことそのものが嫌いになるきっかけにもなりかねません。
やめる判断の目安は、始めた動機と現在の様子。
本人が望んで始めたか?習い事の前後で元気があるか?を1週間観察してみましょう。
習い事をやめる=失敗ではありません。むしろ、「自分に合わないものをやめる経験」は、自己決定力を育てるチャンスでもあります💡
親の役割は、“先生”ではなく“伴走者”
習い事を通して、親も熱が入りすぎてしまうことがあります。「ここはもっとこうしよう」「練習しなさい」と言いたくなる気持ちもわかります。
でも、親は先生ではありません。
一緒に悩んだり喜んだりする、“応援者”でいることが子どもにとっての安心です。
うまくいったときには思い切り一緒に喜び、落ち込んでいるときにはそっと寄り添う。それが、自信や自己肯定感につながっていくのです🍀
まとめ:習い事は“子どもの人生”の一部
習い事を通して、子どもが何を感じ、何を得ているのか。
その視点を大切にすることで、習い事は“親の満足”ではなく、子どもの“学びと成長”に変わります。
ときにはやめる決断もあり。大事なのは、“自分で決める力”を育てることです。
子どもが心から「やってよかった」と思える経験を、一緒に築いていけたら素敵ですね🌈