「読む力」が未来をつくる。
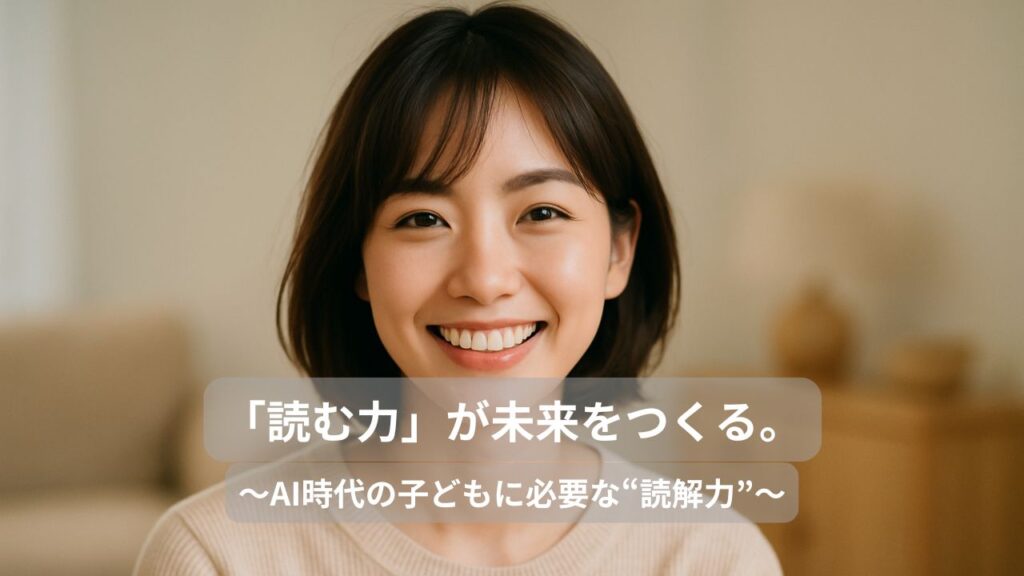
AI時代の子どもに必要な“読解力”の正体と、親ができるシンプルな育て方
最近、「文章を読む力って、本当に必要なんでしょうか?」という声を耳にする機会が増えました。
AIが進化し、音声入力や画像認識が当たり前になった今、「読解力よりも話す力やプログラミングスキルの方が将来役に立つのでは?」と感じる保護者もいるかもしれません。
けれど、実は今の時代だからこそ、読む力=読解力が子どもたちの未来を支える“基盤”になります。
読解力は「すべての学びの土台」
読解力は、国語のためだけにある力ではありません。
問題文を読み取る、説明を理解する、文章から背景や意図をくみ取る。
これらは、算数の文章題にも、理科の実験手順にも、社会の資料読み取りにも必要です。
東北大学の調査では、小学3年生時点で読解力が高い子どもは、中学進学後にすべての教科の成績が高い傾向にあると分かりました。
まさに「読む力=学力の根っこ」と言えるでしょう。
読解力が育む“非認知能力”
読解力は、数字や暗記では測れない「非認知能力」──つまり、共感力、想像力、考える力も育てます。
物語を読んだとき、「この登場人物、どんな気持ちだったんだろう?」「なぜそう思ったのかな?」と想像することは、他者理解や自己表現の練習になります。
東京大学の研究でも、読書習慣がある子どもほど「自分の意見を説明できる力」が高いという結果が出ています。
AI時代こそ、読解力が差になる
AIは確かに便利です。
検索すれば答えがすぐに出てきますし、音声でも情報が得られる時代です。
でも、AIは「なぜそうなるのか?」「その情報は本当に正しいのか?」という判断や、空気・文脈・感情までは読み取れません。
だからこそ、情報を受け取って「意味を読み解く力」は人間の重要な武器になっていきます。
社会で使う「読む力」は、思った以上に多い
大人になると、日常のあらゆる場面で「読む力」が試されます。
業務のメール、契約書、マニュアル、就業規則、保険の説明書──
読解力がなければ、大事な内容を誤解してトラブルになってしまう可能性も。
実際、ある人材企業の調査では「企業が新卒社員に最も求める能力」は「コミュニケーション力」でした。
それは、単に“話す”ことではなく、「伝え合う・理解し合う」力。つまり、読む力が大きく関係しているのです。
読解力が低いと起こる困りごと
読解力が不足していると、次のような問題が起こりやすくなります。
- 勉強の理解が浅く、成績が伸び悩む
- ネット情報に振り回され、フェイクニュースを信じてしまう
- 感情の言語化ができず、自分の気持ちを伝えられない
- 人間関係での誤解やトラブルにつながる
東京都教育委員会の報告でも、読解力の低さが自己肯定感や学習意欲の低下と関係していると指摘されています。
家庭で育てる“読む力”の習慣
読解力は、学校だけで育つものではありません。
むしろ、家庭での「日常的な読み聞かせ」や「会話の時間」が大きな影響を与えます。
たとえば:
- 毎日10分、子どもと一緒に絵本を読む
- 「どこが面白かった?」「どんな気持ちになった?」と感想を聞く
- 読んだ内容について一緒に考える
こうしたやりとりは、子どもにとって“考えるクセ”を育て、言葉と心を結びつけるトレーニングになります。
親ができる、読解力サポート3選
- 本を読む時間を日常に取り入れる
→ 親自身も読書する姿を見せると、子どもは自然に真似します。 - 子どもの話を、最後まで聞いてあげる
→「それでどう思ったの?」「どうしたかったの?」という問いかけで、言葉にする練習を促せます。 - すぐに答えを教えない
→ ちょっとだけ待つことで、子どもは自分の力で考え始めます。
おわりに:読む力は、生きる力。
「読む力があれば、勉強ができる」──それももちろん大切です。
でも、もっと大切なのは、読む力があれば、考えられること。感じられること。判断できること。
それができる人は、どんな時代でも、どんな環境でも、生きていけます。
AIにできない“人らしさ”を育てるために、今日からおうちで、小さな「読む習慣」を始めてみませんか?



