子どもの性格は“育てられる”
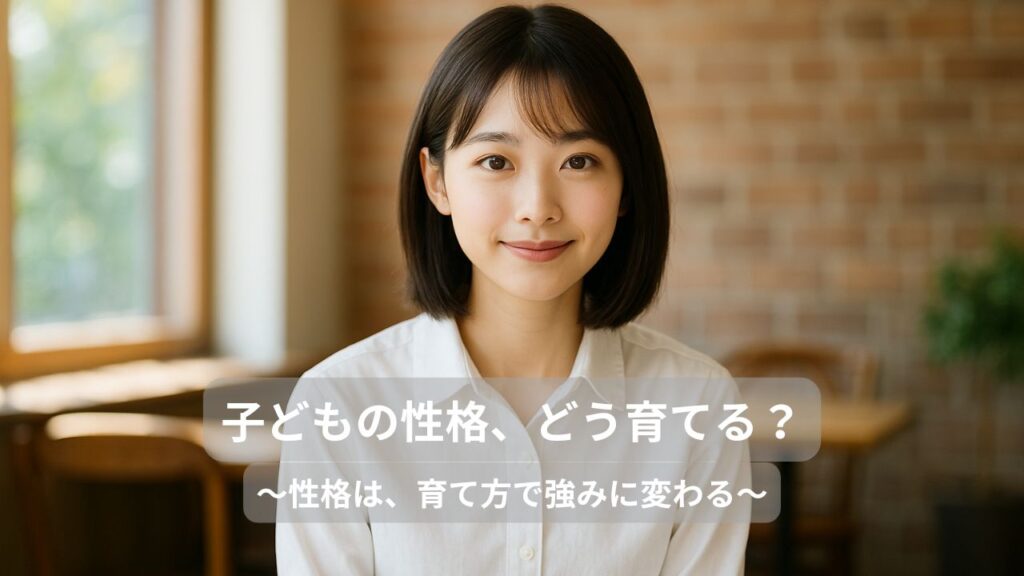
そしてそれは、生きる力になる。
「うちの子、性格的に○○だから仕方ない」
そう感じたこと、ありませんか?
育児をしていると、どうしても目の前の“子どもの性格”に目が向きます。
落ち着きがない、わがまま、恥ずかしがり屋、頑固…。
こうした特徴を「個性」として伸ばすのか、「直すべき」なのか、悩む親は多いでしょう。
でも、そもそも性格って「直すもの」なのでしょうか?
答えは――性格は、育てることができるものです。
「性格は生まれつき」と思っていませんか?
心理学の研究では、性格の約半分は環境や経験によって変わると言われています。
特に、幼少期の子どもにとっては、家庭での関わり方や日々の体験がそのまま“性格の土台”を作っていくのです。
たとえば、内気で引っ込み思案な子でも、小さな成功体験を重ねることで自己表現が上手になる。
癇癪を起こしやすい子も、感情の言語化や共感的な声かけで、気持ちを自分で整理できるようになる。
「性格は行動の積み重ねで形づくられる」という考え方が、今では主流になりつつあります。
性格を育てる3つの要因
性格を形成する要因は、大きく3つあります。
1つ目は、「気質」。
これは生まれつきの特徴。慎重・大胆、内向・外向など、反応の傾向です。変えにくい部分ではありますが、受け入れて活かすことができます。
2つ目は、「家庭環境」。
親の声かけやしつけ、安心感のある関係性が、子どもの性格に大きな影響を与えます。
3つ目は、「成功体験」。
子ども自身が「やってみた」「できた」という実感を得ること。この喜びの積み重ねが、自信と主体性を育てていきます。
性格は“生きる力”の基盤になる
文部科学省が掲げる「生きる力」――それは、学力だけでなく、社会を生き抜くために必要な力。
自己肯定感、課題解決力、対人関係力、自律性、挑戦力。
これらの力は、すべて性格と深く結びついています。
たとえば、挑戦力には「楽観的な性格」や「好奇心」が必要ですし、課題解決力には「粘り強さ」や「柔軟性」が欠かせません。
つまり、性格を育てることが、そのまま“生きる力”を育てることに直結するのです。
性格を育てる親の関わり方
では、具体的にどのように関わればいいのでしょうか。
たとえば、子どもが失敗したときには、叱るのではなく「悔しかったね」と気持ちに寄り添ってあげる。
成功したときには、「すごいね!」ではなく、「最後までやったからできたね」と行動を具体的に認める。
感情の名前を一緒に見つけるのも効果的です。「怒ってる?」じゃなく「それって悲しかったのかな?」と、子どもの内面に言葉を与えることで、自分の気持ちをコントロールできるようになります。
家庭でできる“性格を育てる習慣”
性格を育てるのに、特別な教育法や教材は必要ありません。
たとえば――
- 寝る前に「今日うれしかったこと」を話す時間をつくる
- 「ありがとう」や「ごめんね」を親が積極的に伝える
- 子どもの「できたこと」をカレンダーに書き出していく
- 感情カードや絵本を使って、気持ちを表現する練習をする
こうした日々の積み重ねが、子どもの性格を育てる土台になります。
短所は、見方を変えれば長所になる
「困った性格」も、見方を変えれば武器になります。
- 落ち着きがない → 行動力がある
- 頑固 → 意思が強い
- 心配性 → 注意力が高い
- おしゃべり → 表現力が豊か
- 恥ずかしがり屋 → 観察力が高い
性格は、直すのではなく活かして伸ばすもの。
そしてその視点を与えるのが、親の役割なのです。
さいごに
「性格」は変えられない――。
そう思い込んでいたら、親子にとってもったいないかもしれません。
性格は、育てられます。
そしてその性格は、子どもが将来、社会の中で自分らしく、たくましく生きていくための基盤になります。
今日からできることを、ひとつずつ。
あなたの関わりが、子どもの未来をつくっていくのです。



